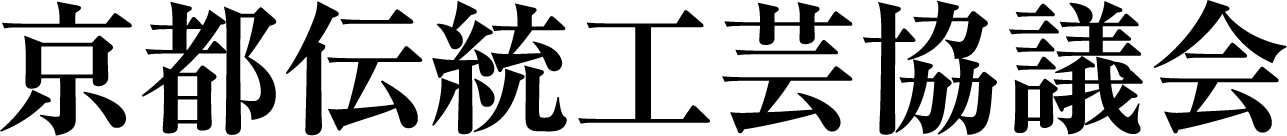色紙短冊和本帖
Shikishi, Tanzaku and Waboncho paper
色紙はもともと染紙のことを指し、この名は屏風や障子に詩歌などを書き入れる場所を取ることを色紙型と呼んだことに由来します。短冊は、短籍、短策、短尺とも書き表され、色紙より小さく略式化されたものとされています。
色紙・短冊ともに元来、宮廷や寺院などで多用され、京都が発展の中心でした。なかでも、金銀の泥絵(かきえ)や切箔、野毛を蒔くなどの加工を施す職人は、ほとんど京都から世に出ました。
現在も全国の色紙・短冊の9割以上を京都が生産しており、また、これらの製造技術を生かした和文具や雑貨なども製作されています。
色紙とは、もともと染紙のことを指す。この名は、屏風や障子などに詩歌その他を書き入れる場所(余地)を取ることを色紙型と呼んだことに由来する。
平安時代、歌集や詩書の中には染紙を用いて装飾性をもたせたものが数多くあった。この中には、金銀の泥紙や切箔さらには野毛などを蒔いた華麗なものも多かったが、これが現在のような色紙や短冊として完成するのは鎌倉時代からであろう。
短冊は、短籍、短策、短尺とも書き表された。懐紙や色紙よりは小さく、略式化されたものが短冊とされていた。室町時代の初期にはかなり盛んになっていたようで、それは後小松天皇御製料紙や豊公醍醐の花見の短冊などでもわかるとおり、狩野派や土佐派の流れをもつすばらしい金銀泥絵であった。
色紙および短冊は。一般に経師により作られていたが、それには朝廷用の一切の紙に関する仕事に携わっていたもの、もっぱら寺院を得意先にしたものがあったが、さらには絵草紙屋でも一般向けに色紙や短冊類を販売していた。
元来、宮廷や寺院などで多用された色紙・短冊においては、京都にその発展の中心があり、中でも金泥や、金銀箔により加工する職人は、ほとんどが京都から世に出た。
現在、京都では全国の色紙・短冊の9割以上も生産しているが、近年、書道の復興や和歌、俳句の流行などにより、その需要が増加しつつある。業界にとっては嬉しい風潮といえるが、それに応えていくためにも、良質の和紙の確保と後継技術者の育成に努力している。
なお、「京の色紙短冊和本帖」は、特許庁の商標原簿に登録された、京都色紙短冊協同組合の地域団体商標である。
関連団体
Related Organization
京都色紙短冊協同組合
Address
〒604-8111
京都市中京区三条通高倉東入桝屋町57 株式会社長谷川松寿堂内
TEL
075-255-1515
FAX
075-231-1571
Address
TEL
FAX