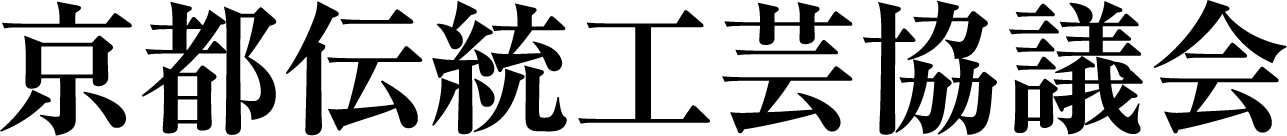神祇装束調度品
Shinto Paraphernalia and Attire
神道の祭祀や祭礼に用いる祭器具や衣裳を、神祇装束調度品といいます。祭器具には、三方や神殿などの木具類、鏡、御簾、雅楽器などがあります。また、衣裳は、衣冠、狩衣、烏帽子など、神職が着用する伝統的な衣服のことを指します。
その種類は多様であり、いずれもが少量生産され、手づくりが大部分を占めます。
皇室の所在地であった京都は、各種の式典、行事も多く、古くから神社の神事も盛んであったため、神祇装束調度品の一大中心地となり、現在も伝統行事や文化事業等のために、染織、木工、金工、漆芸など様々な伝統技術を駆使し製作が行われています。
神具は祭具とも呼ばれ、その名のとおり祭祀や祭礼に用いる器物のことである。その種類は多様であり、何れもが少量生産、大部分が手作りである。伊勢大神宮の御遷宮調度師として名高い坂本家が世に出るのは江戸中期のことであるが、もちろんそれ以前から、京都の神具は全国に先んじて発達していた。ちなみに、現代においても、式年遷宮の神宝装束は京都の業界で製作されている。
京都は明治維新まで皇室の所在地であり、各種の式典、行事も多く、古くから神社の神事も盛んであったために、それらの調度や衣装(装束)などを作る専門家を多数必要とした。
一方、装束であるが、神職(神主)は狩衣、浄衣を通常着用するが、祭祀や祭礼にあたっては束帯、衣冠を着けるのがならわしである。もともと束帯は正式な朝服であり、衣冠は宿直の際などに用いる略服であったが、いつしか衣冠も束帯と同じく朝服となり、有位の者が着用するのを許され、現在では神職の正装となっている。室町時代以前より西陣で織り続けられてきたが、このうち、山科家は宮中の装束を、そして高倉家は将軍家や諸大名の装束を、それぞれ西陣の御寮織物司に命じて作らせていた。また、これは神具においても同様で、祭礼に用いる神輿、鉾、錦旗などの飾り物は、そのほとんどが西陣の錦綾や金欄などによっている。
第二次大戦後、一方においては、神社をはじめ各種会館やホテルなどで神式の結婚式場を設けるところが増え、あわせて伝統行事の全国的復活など、神祀調度や装束に対する需要は今後も増える傾向が続くものと期待される。
関連団体
Related Organization
京都神祇調度装束協同組合
京都神祇工芸協同組合
Address
〒602-8011
京都市上京区烏丸通下長者町桜鶴円町 護王神社内
TEL
075-441-5458
FAX
075-414-0255
Address
〒603-8422
京都市中京区間ノ町丸太町下ル大津町661-1 株式会社山岡商店内
TEL
075-231-0393
FAX
075-231-0587