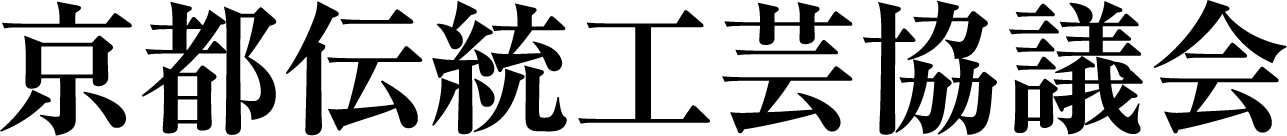神仏具金物
Kyoto Shinbutsugu Kanamono
神仏具金物は、神社やお寺における建物の装飾、香炉やおりんといったお仏壇へお参りするための道具などを指し、神道や仏教をはじめとする宗教の施設や儀式、行事に用いられます。
京都では、室町時代の末期に、京都市の中心地「釜座」で集団で工房を構えていた鋳師(いもじ)の中から、仏具を手がける者が出てきたことが生産の起源とされます。
型の生成から鋳造、加工など長い時間と工程を経て完成し、古くから受け継がれてきた生産技術と体制によって、現在も大部分が職人による手作業で制作されています。
古都・京都は、古来文化の中心都市であるとともに仏教や神道をはじめとする様々な宗教活動においても、常にその中心地であった。宗教活動は、それぞれの教義に基づく多くの行事に支えられ、同時にそれを演出する各種の宗教用具を必要としてきたことから、京都においてその生産を担う神仏具金物の産地がおのずと形成された。
京都における宗教用具の生産の起源は古く、神仏具金物においては室町時代の末期にまで遡る。『金工史談』(香取秀真著)によると、今に伝わる銅鐘のいくつかに「三条」「釜座」という銘文を有するものがあり、これが現在、資料によって知ることができる最も古い京都在住の鑄師の作品ということになる。
「釜座」とは現在の京都市の中心部で、鑄師が集団で工房をかまえていた。当時においては、鑄師は厨房用の日常品を本業とし、茶の湯の隆盛につれて茶の湯釜を製造したり、注文に応じて、燈籠や銅鐘を造っていた。彼らの中から、次第に仏具を手がける者が出てくるわけであるが、上述の様に、仏具の需要を生み出す背景があった。江戸時代には、かなりの仏具師の存在が文書よりうかがわれる。ただし、彼らの多くは、前記の「釜座」ではなく、当時の市街地の周辺部に工房をもっていたようである。
以来、今日に到るまで、各種の宗教教義や儀礼に基づいた様々な道具類を製作し続けている。その間、各時代の要求を取り入れて、各々の時代にかなう変化を重ねながら、しかも一貫して伝統を遵守する生産機能と体制を堅持してきた。
それゆえ京都の神仏具金物は、大量生産には到底なじまず、現在も大部分を手作業により製作しており、その優れた技術や品質は高く評価されている。 そして、宗教用具としての品位と本質をわきまえた上で、生産工程の専門化・細分化を進めるとともに、品質面での改善・改良にも前向きに取り組んでいる。
関連団体
Related Organization
京都神仏具金物工業協同組合
協同組合 京都金工センター
Address
〒604-8227
京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町436 興和セントラルビル7F あおい税理士法人内
TEL
075-222-8234
FAX
075-222-8225
Address
〒601-8206
京都市南区久世大薮町232-1
TEL
FAX