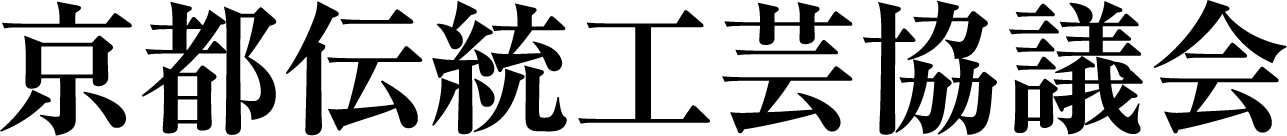京竹工芸
Bamboo Ware
竹の歴史は古く、正倉院には竹を用いた楽器や箱などが所蔵されています。京都では、平安時代になると建材として使用されるようになり、室町時代以降は茶道具の製作のために欠かせない素材として、重宝されるようになりました。
京都は、竹の生産地としての風土条件にも大変恵まれており、良質な竹を育みます。
その素材の持ち味を生かして、材料として伝統的な技術で一次加工する京銘竹や、華道や茶道の道具類はもちろん、家具調度品や照明器具など幅広い京竹工芸品が生み出されています。
竹は原始時代にはすでに用いられていたが、滑沢で強く、その上弾力性にもすぐれて、また乾湿にも歪みがこない特徴を思えば当然のことではある。
正倉院には、竹を用いた楽器をはじめ、箱や華籠その他多数の遺品が保存されているが、平安時代になると、建材としても随所に使われるようになる。また同時に、矢や鞭などの武器、農耕・漁猟の道具など、日常生活の細かな部分まで広がってゆく。
鎌倉時代の終わり頃から室町時代にかけて、茶道具を製作するために欠かせぬ素材として、竹はますます重宝されるようになってゆく。
江戸時代初期には、竹細工、柄杓師が活躍し、将軍家の御用をつとめるほどになる。中期になると、大竹を輪切にした花器や柄杓などの道具を作る職人が京極の二条や四条周辺に多く住んだ。
京都は竹の生産地としての風土条件に大変恵まれているといえる。山に囲まれた盆地は寒暖の差が激しく、土壌も肥沃である。このような風土と文化都市としての恵まれた環境のもと、京都はまた竹の都としても知られてきたのである。
京都の竹工芸品の特色は、竹そのものの持ち味をそのまま生かしているところにある。これは、それだけ京都の竹が素材としてすぐれているということであろう。中でも、嵯峨野の竹は殊に名高い。京都の簾は技術的に群を抜いており、手作りの高級品は京都でのみ作られているほどである。
この数年来、人々は生活の中にゆとりや潤いを真剣に求めだしている。それにつれ竹製品に対する関心も高まりつつあり、また、外国への輸出も、これまで以上に期待がもてそうである。
「京銘竹」、「京竹工芸」は、京都府伝統工芸品の指定を受けている。
また、「京竹工芸」は、特許庁の商標原簿に登録された、京都竹工芸品協同組合の地域団体商標である。
関連団体
Related Organization
京都竹工芸品協同組合
京都竹材商業協同組合
Address
〒605-0875
京都市東山区鐘鋳町419
TEL
075-561-3624
FAX
075-541-0084
Address
〒602-8062
京都市上京区油小路通上長者町下る亀屋町135 有限会社横山竹材店
TEL
075-411-3981
FAX
075-432-5876