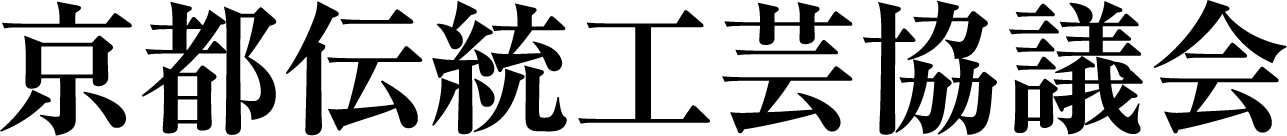京焼・清水焼
Kyoto Ceramic Ware
京焼・清水焼は、清水坂界隈や京都市内各地の窯元で焼かれてきた陶磁器の総称です。ほとんどが手づくりによるもので、多品種少量生産が特徴です。
17世紀に野々村仁清、尾形乾山などの名工の登場により、京焼・清水焼は他地方にまで影響を及ぼすようになりました。
その後も多くの才能豊かな名工が独自のデザイン・技法を生み出し、京都は日本陶芸の中で独自の地位を築いてきました。
高い意匠力と多彩な技術に基づいた華麗で雅な陶磁器が、窯元ごとに独自の作風でつくられています。
京都におけるやきものは千二百有余年、僧行基が清閑寺(京都市東山区清閑寺)に窯を築いて土器を製造しており、その遺跡が茶碗坂といわれている。
室町時代には、明から伝えられた交趾釉法の内焼が二条押小路で行われている。色絵陶器の誕生である。他方室町末期には茶の湯の流行に伴い、瀬戸から呼び寄せた陶工に、粟田や音羽などで茶陶を作らせた。
京焼・清水焼の歴史に欠かせぬ人物に、野々村清右衛門(仁清)がいる。丹波の陶工であったが、入落後、茶器を作り、錦手の秘法を会得する。それはまことに華麗で優雅な色絵陶器であり、京焼・清水焼のひとつの頂点ともいえるものであった。また、仁清から直接手ほどきを受けた尾形乾山は、兄光琳に優るとも劣らないほどの装飾性に富んだ絵模様で、独自の意匠性を加えた。
江戸の末期になると、大雅、玉堂など、中国の文人画の流れをくむ南画家が数多く出たことが影響し、京焼・清水焼は色絵陶器と奥田潁川によって開発された磁器に中国風土を加味した二つの世界が生れる。その後、青木木米や仁阿弥道八、永楽保全などの名工が続き、伝統的な京焼・清水焼の全盛をもたらし、そのまま今日の香り高い作品に受け継がれている。
現在、京都では陶土を産しないので、天草、柿谷、信楽、伊賀などの粘土を移入して使っている。これを手工法、ロクロ法、石膏型による型押し法、流し込み法など、製品によってそれぞれに成形する。焼成は、従来、京式登り窯によっていたが、現在では電気釜やガス釜に移行している。このことにより工程はずいぶん合理化され、それだけ生産性も高まった。また山科や炭山地区に陶工たちが集団移転し、新しい京焼・清水焼の創造に意欲を燃やしている。
関連団体
Related Organization
京都陶磁器協同組合連合会
Address
〒607-8322
京都市山科区川田清水焼団地町6-2 コーポきよみず203
TEL
075-582-3113
FAX
075-582-3114
Address
TEL
FAX